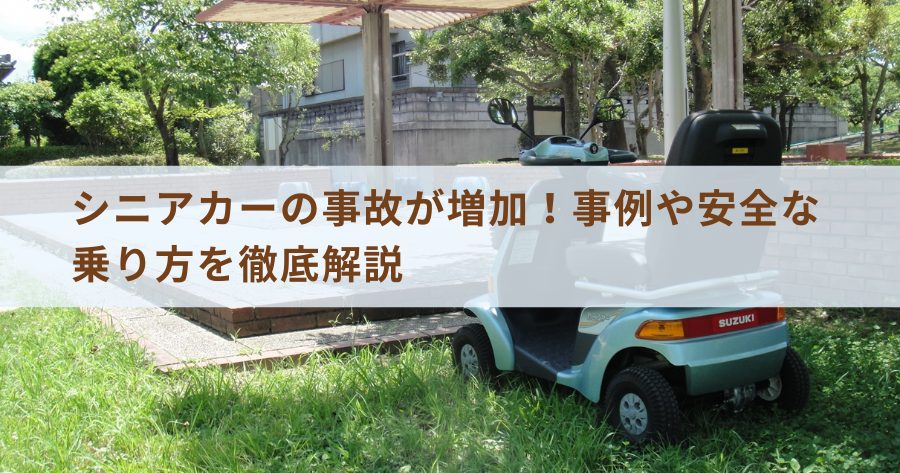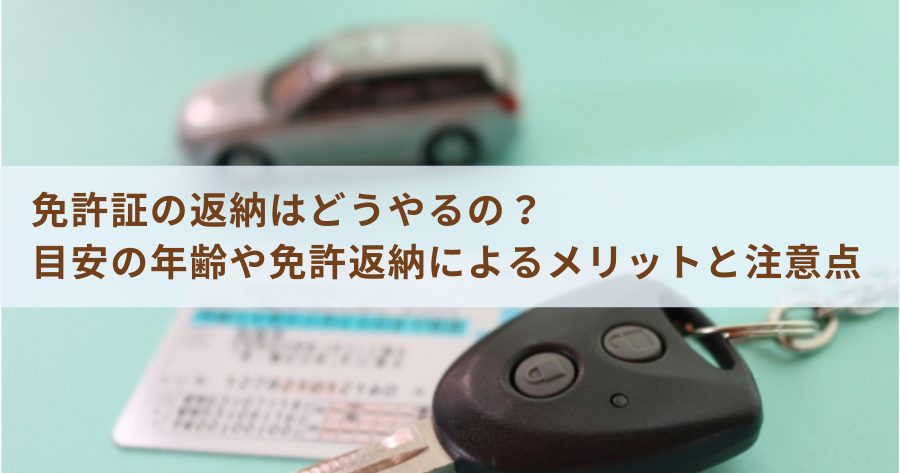セニアカーの値段や補助金について解説!購入・レンタルどちらがおすすめ?
- 2024.01.15
最終更新日 2024.6.4.
【シニアカーのエキスパート!シンエンス監修】スズキのセニアカーは、シニアカー(電動カート)の中でも特に人気のモデルです。
この記事では、セニアカーの利用を検討している方に向けて、セニアカーの特徴や料金、補助金についてまとめました。
新品や中古で購入するかレンタルするか、それぞれどのようなメリット・デメリットがあるのかも解説します。

電動車いす、電動カートのレンタル・販売を行う専門会社。高い技術力と豊富な実績で運転指導からメンテナンスまでトータル的にサービスを提供。そのほか歩行器のメーカーとしても、超コンパクトサイズから大型モデルまでラインナップ豊富に展開。
▷コーポレートサイトはこちら
目次
「セニアカー」とは?シニアカーとは何が違うの?

セニアカーとは、スズキのハンドル形電動車いす(シニアカー)の商品名で、商標登録されています。
セニアカーは、いわゆるシニアカーのことです。最高時速は6kmで大人の早足の速さとほぼ同じです。
法律上、歩行者扱いとなり、歩道を走行することができるため運転免許も必要ありません。
セニアカーの値段は?【新品・中古・レンタル】
スズキのセニアカーの値段をモデル別にまとめたので、購入の参考にしてください。
| 型番 | 新品 | 中古 | レンタル |
|---|---|---|---|
| ET4D(イエロー、ブルー、レッド) | 418,000円(非課税) | 100,000円〜(販売店によって差があります) | 月々2,000円~(介護保険適用) |
| ET4D(ホワイト) | 433,000円(非課税) | ||
| ET4E | 320,000円(非課税) |
ET4Dは2023年12月22日にモデルチェンジした最新モデルです。
スズキ セニアカーの3つの魅力
セニアカーの魅力は大きく分けて4つあります。
①:介護保険でレンタルできる
②:補助金の対象になる
③:歩道を走れるので免許無しで乗れる
④:非課税で消費税がかからない
それぞれ詳しく紹介します。
①:介護保険でレンタルできる
介護保険制度を利用することで、レンタル費用の経済的な負担を大幅に軽減することが可能です。
レンタル料の自己負担は原則として1割となり、所得に応じて2〜3割に増加する場合もあります。それでも全額自己負担する場合と比較してかなりのコスト削減になるでしょう。
介護保険を利用するためには、まず要介護認定を受ける必要があります。ただし、要支援1、2や要介護1の方の場合は、基本的にシニアカーのレンタルは認められていません。
しかし、日常の歩行に困難がある場合や、移動の支援が必要と認められれば、これらの認定でも介護保険を利用してシニアカーをレンタルすることが可能になります。
②:購入時は補助金の対象になる
セニアカーは介護保険適用の福祉用具として認められているので、条件次第で補助金の対象になります。補助金は購入金額の1/3で、上限10万円が相場のようです。
補助金の対象になるかは自治体によって違いますが、対象者として多いのは以下です。
【補助金の対象者例】
■住民基本台帳に記録されている本人
■自動車運転免許証を自主返納している
■介護保険の認定を受けていない
■税金を滞納していない
■他の制度による補助を受けていない
このほかに、申請時の年齢(65~70歳前後)や対象製品などが指定されていることもあります。
補助金を受けることで購入費用をおさえられますね。
対象や申請方法を含め、購入前にお住まいの自治体へ確認してみましょう。
③:歩道を走れるので免許無しで乗れる
セニアカーは、ハンドルがついているので軽車両に思われる人もいるかもしれませんが、道路交通法上では歩行者扱いです。そのため、歩道を走行することができます。
歩行者扱いなので、免許が必要ありません。誰でも気軽に乗車できます。
また、歩道を走れるので交通事故のリスク低減にもつながるのがポイントです。
免許の返納を考えている方の次の移動手段として悩んでいる方に、セニアカー(シニアカー)はおすすめできます。
④:非課税で消費税がかからない
セニアカーは非課税対象なので、消費税がかかりません。
自動車税も不要です。
購入やレンタルのハードルが下がりますね。
セニアカーは購入すべき?レンタルすべき?

セニアカーは非課税ですが、新品を購入する場合はまとまったお金が必要になるもの。補助金の対象であっても、20〜30万円ほどは必要になる計算です。
費用が気になる方は、購入以外にも介護保険制度を使ってレンタルする方法もあります。
購入とレンタル、それぞれのメリットとデメリットを見ていきましょう。
セニアカーを購入するメリット・デメリット
セニアカーを購入するメリットとデメリットです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 介護保険制度が使える | 購入にまとまったお金が必要 |
| 中古品は安く購入できる | 保険加入など初期コストがかかる |
| 購入時に補助金がある(自治体による) |
セニアカー購入のデメリットは購入時にまとまったお金が必要な点です。万が一に備えて任意保険に加入する場合のコストもかかります。
対してメリットは、購入時に自治体からの補助金が出たり、対象者は介護保険制度が使えたりしてお得に利用できることです。
購入したセニアカーは使いやすいようにカスタマイズすることも可能なので、愛着を持って使えます。
購入を検討している人は、シニアカーや電動車いすの専門店「げんき工房」がおすすめです。
新品・中古品どちらも試乗ができ、アフターサポートも充実しているので安心。丁寧な商品説明もしてもらえるので、すぐに使いこなせるようになれます。
げんき工房のスタッフが、ご利用車のご自宅へ伺い試乗体験することも可能です。げんき工房では中古の場合、1年保証(売価10万円未満は3ヶ月)がつきます。
購入を検討されている方は、ぜひ『げんき工房』のサイトをチェックしてみてください。
セニアカーをレンタルするメリット・デメリット
こちらは、セニアカーをレンタルする場合のメリットとデメリットです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| コストがおさえられる | カスタムができない |
| 介護保険適用なら1割〜3割でレンタルできる | 希望モデルをレンタルできないことがある |
| レンタル業者による定期メンテナンスがある | 介護保険適用外になったら返却が必要 |
セニアカーレンタルのデメリットは、身体状況の改善で介護保険適用外になると、返却しなければなりません。
また、希望通りのモデルや色のセニアカーに空きがない場合があります。レンタルしたセニアカーはカスタマイズもできません。
メリットとしては、購入よりもレンタルの方がコストがおさえられる点があります。購入に比べ、初期費用は圧倒的に安いうえ、定期的なメンテナンスも受けられることがほとんど。
身体状況や使用シーンの変化に応じて、モデルの変更にも対応してもらえます。
まずはシニアカーをお試ししてみたいという方には、レンタルがお得です。
レンタルを検討している人や保険についてわからないことがある方は、シニアカーや電動車いすの専門店「げんき工房」へお気軽にご相談ください。
セニアカーとあわせて使いたい「モニスタ」のGPS見守りサービス

セニアカーとあわせて使いたいのが、「モニスタ」です。
【モニスタとは】
電動車いす用のGPS見守りサービス。GPSで位置情報や走行ルート、安全運転レベルなどが見守れるため、離れて暮らしていても安全確認が可能。消耗部品交換時期が近づくと、電話で知らせてくれ専門業者が交換するサービスもある。
セニアカーにモニスタを取り付けると、登録したスマートフォンやタブレット端末から走行が見守れる仕組みです。
外出している高齢者家族の状況や、離れて暮らす高齢の親が安全に外出できているかなど、セニアカー利用の不安解消にぜひ「モニスタ」を活用してみてください。
セニアカーを導入することで、歩行に不安がある人も活動の場所が広がり便利になります。そこにモニスタのGPS見守りサービスがあれば、セニアカーの便利さに安心をプラスできますね。
セニアカー購入やレンタルを検討している場合、見守りGPSサービスについてはモニスタまでお気軽にお問い合わせください。
まとめ:セニアカーはスズキが販売する人気シニアカー

スズキが販売するハンドル形電動車いす、セニアカーについて紹介してきました。
セニアカーの主な魅力はこの4点です。
①:介護保険でレンタルできる
②:補助金の対象になる
③:歩道を走れるので免許無しで乗れる
④:非課税で消費税がかからない
道路交通法では歩行者扱いになるので、免許不要。誰でも手軽に乗れます。
また、消費税がかからないうえ、自治体によっては購入時に補助金が降りることもあり、導入ハードルが下がります。中古品購入や介護保険適用のレンタルも可能です。
そんな人気のセニアカーですが、離れて暮らす高齢家族への導入が不安な人は「モニスタ」のGPS見守りサービスがおすすめです。
セニアカーとセットで利用すれば、便利と安心のいいとこどりができます。
ぜひモニスタの利用もあわせて検討してみてくださいね。