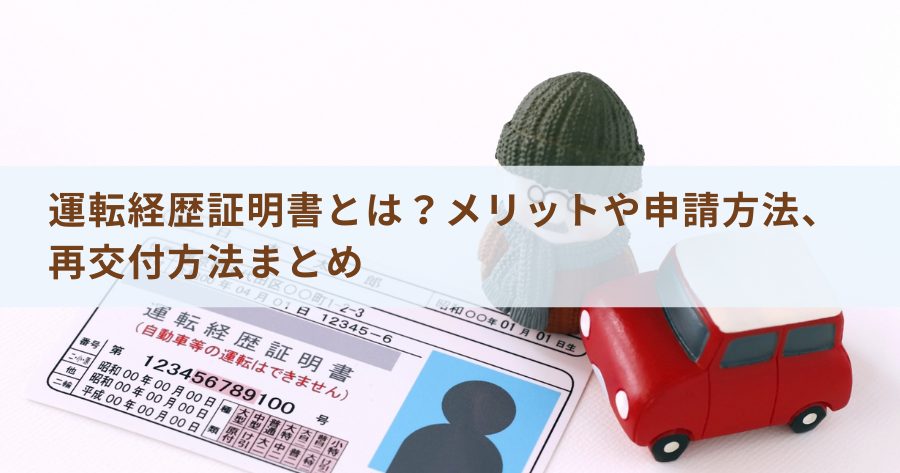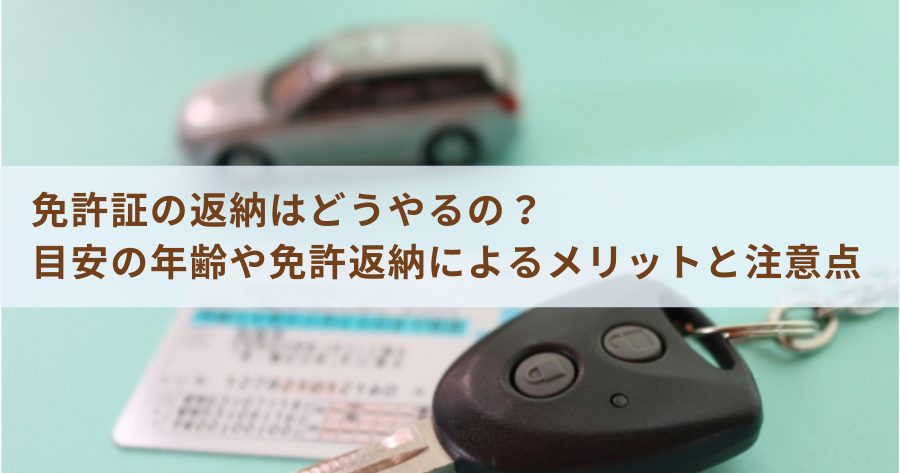高齢者の運転による事故を防ぐには?高齢者マークや免許返納についても解説
- 2024.03.27
最終更新日 2024.4.26.
【シニアカーのエキスパート!シンエンス監修】高齢者の運転による事故をニュースなどで見かける日も多く、高齢になった家族の運転を不安に感じる方も多いかもしれません。
この記事では、高齢ドライバーとその家族に向けて、事故のリスクや家族でできるサポートをまとめました。
高齢ドライバーが安全運転のための知識として知っておきたい、高齢者マークや免許更新、免許返納についても解説します。

電動車いす、電動カートのレンタル・販売を行う専門会社。高い技術力と豊富な実績で運転指導からメンテナンスまでトータル的にサービスを提供。そのほか歩行器のメーカーとしても、超コンパクトサイズから大型モデルまでラインナップ豊富に展開。
▷コーポレートサイトはこちら
目次
高齢ドライバーとは何歳から?
世界保健機関(WHO)では65歳以上を高齢者としています。
日本では、70歳から高齢者講習が義務付けられており、75歳以上のドライバーは認知機能検査も受ける必要があります。(参照: 全国交通安全協会)
これらの年齢基準は、交通事故のリスクを低減し、ドライバー自身の安全を確保するために設けられているものです。
70歳以上の運転には高齢者マーク(もみじマーク)の着用が必要

近年、高齢者マークを付けた車を目にすることが増えていると思います。これは、70歳以上の高齢ドライバーに対する周囲の配慮を促すための標識です。
高齢者マークには、旧型の『もみじマーク』と新型の『四つ葉マーク』の2タイプがあります。現在はどちらのマークも利用が可能です。
高齢者マークは、70歳以上が努力義務となり、着用していなくても現在は罰則はありません。(参照: 道路交通法)
しかし、他の運転者に高齢者の存在を知らせ、安全運転を促進するための重要な役割を果たすマークとして使用は必要でしょう。
あわせて読みたい記事:「高齢者マークとは?何歳から使用すべきかメリットなどあわせて紹介」
高齢者の運転はなぜ危ない?気をつけたい事故のリスク

高齢者の運転は事故のリスクが高くなります。
その理由は大きく3つあります。
①:体力の低下により集中力を保つのが難しくなる
②:動体視力や認知機能の低下により、とっさの判断をとるのが難しくなる
③:長年運転してきたという過信による不注意が増える
それぞれ詳しく見ていきましょう。
①:体力の低下により集中力を保つのが難しくなる
誰しも、年齢とともに体力や持続力が低下していきます。
特に、長時間の運転では集中力を保つのが難しくなるものです。長距離や夜間の運転は、高齢ドライバーに限らず疲労が溜まりますよね。
集中力を維持しにくい高齢ドライバーは、疲労により反応速度が低下しやすく、事故のリスクが高くなります。特に交通量の多い地域や初めての場所では、継続的な注意力が必要です。
高齢ドライバーは、休憩を多く取ったり長時間の運転を避けるなど工夫しましょう。
②:動体視力や認知機能の低下により、とっさの判断をとるのが難しくなる
高齢になると、動体視力や認知機能が低下します。急な状況変化に対応する能力が衰えるということです。
交差点での急な車の出現や歩行者の動きに、迅速かつ適切に反応するのが難しくなるので事故につながる可能性が高いです。
高齢ドライバーは、自覚がなくともこれらの変化に注意しましょう。
運転時は適切な速度と距離を保つことが大切です。
③:長年運転してきたという過信による不注意が増える
長年の運転経験による過信は、特に高齢ドライバーにとって危険なポイントです。
基本的な交通ルールの遵守がおろそかになったり、速度制限や信号の変化に適切に反応できないといった不注意が起こりやすくなってしまいます。過信による不注意は、事故に直結することも多いので看過できません。
高齢ドライバーには、自分の運転能力を客観的に評価することが重要です。
これは「自己チェック」と言い換えることができます。自己チェックを行うことで、運転に伴うリスクを減らすことができるでしょう。
また、必要に応じて運転を控える決断をすることも大切です。
これは「安全のための自制」と考えることができます。
自分自身の安全だけでなく、他の人々の安全も考慮するため、運転をするかどうかを慎重に判断することが求められます。
高齢ドライバーの事故を防ぐために家族ができること
高齢ドライバーを持つ家族は、高齢者の運転能力を定期的に評価することが重要です。
まずは、高齢ドライバーの運転する車に同乗し、運転技術や判断力をチェックしてみてください。また適切なタイミングでの免許返納を提案することも、高齢ドライバーの家族にとって重要な役割です。
安全運転や免許返納について定期的に話す機会を持ったり、必要に応じてバスや電車、タクシーなど自家用車に代わる移動手段を提案したりすることが事故を未然に防ぐキーポイントとなります。
高齢者の免許返納はいつがタイミング?
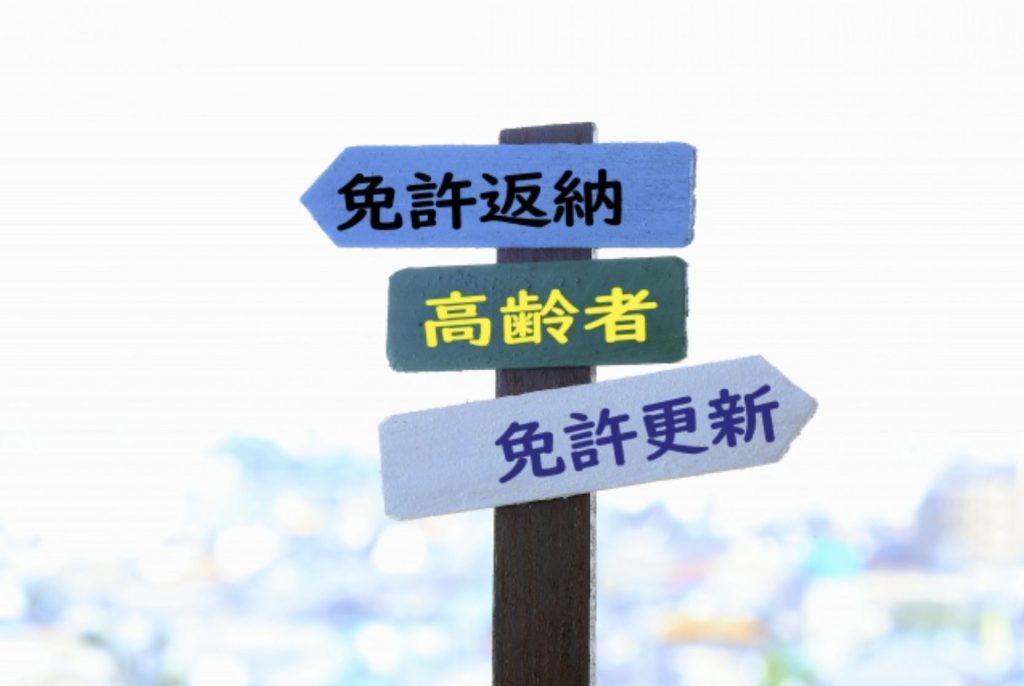
免許返納のタイミングは、ドライバーによってさまざま。これは、現在の法律で運転可能な年齢に上限が設けられていないからです。
しかし、運転に自信がなくなったり、不安を感じ始めたら、免許返納を考える良いタイミングです。
高齢ドライバー自身が安全運転能力を自己評価するのはもちろん、家族や医師の意見に基づいて免許返納を決めるのが理想的です。
詳しくは「免許証の返納はどうやるの?手続き方法や免許返納によるメリットと注意点」の記事で解説していますのであわせてご覧ください。
免許返納すると運転経歴証明書が交付される
免許を返納すると、運転経歴証明書が交付されます。
この証明書は公的な身分証明書として利用できるほか、自治体によっては公共交通機関や飲食店などでの割引サービスが受けられます。
タクシーの割引やスーパーの宅配サービスなどに使えるといったものです。
シニアカーの専門店「げんき工房」では、運転経歴証明書の提示で電動カート購入特典があります。
免許返納は、社会的なサポートと連動しています。運転をやめる決断をしたら、生活の質を維持するためにも免許返納をおこないましょう。
あわせて読みたい記事:「運転経歴証明書とは?メリットや申請方法、再交付方法まとめ」
免許返納した後はシニアカーがあると日常の移動が便利になる
免許返納後は、シニアカーや電動車いすがあると日常の移動に役立つでしょう。
シニアカーや電動車いすは、レンタルする場合に介護保険制度や補助金の対象となるので、レンタル前に自治体の窓口やソーシャルワーカーに相談してみるのがおすすめです。自家用車のような事故リスクはぐっと下がります。
とはいえ、事故や予期せぬトラブルが起こらないわけではありません。
そんな不安を解消してくれるのが「モニスタ」です。
【モニスタとは】
電動車いす用のGPS見守りサービス。GPSで位置情報や走行ルート、安全運転レベルなどが見守れるため、離れて暮らしていても安全確認が可能。消耗部品交換時期が近づくと、電話で知らせてくれ専門業者が交換するサービスもある。
シニアカーや電動車いすに「モニスタ」を取り付けていれば、遠方に住むご家族もご利用者の移動を見守ることができます。
また、電動車いすのパーツ交換目安も教えてくれるので、故障やトラブルも未然に防げて安心です。
あわせて読みたい記事:「【シニアカー完全ガイド】免許や補助金、安全な使い方を解説!」
まとめ:高齢者の安全運転を家族でサポートしよう

高齢ドライバーの安全運転には、家族のサポートが不可欠です。
運転技術の確認や免許返納の提案など、高齢ドライバーが安全運転を続けられるようにするのは家族の大切な役割の1つともいえます。
移動手段がなくなることで免許返納を躊躇している場合は、シニアカーや電動車いすの利用を考えてみてください。自家用車を運転するより事故リスクが低く、高齢者が安全に外出できる方法です。
しかし、電動車いすでも事故リスクやトラブルがゼロになるわけではありません。
そんな不安には、「モニスタ」の利用がおすすめです。GPS見守りサービスなので、ご家族がご利用者の移動を確認できます。これにより、万が一道に迷ってしまったときや、電池が切れて立ち往生してしまったときも、迅速な対応が可能です。
高齢者が安心して外出できるサポートとしてぜひモニスタの利用を検討してみてください。