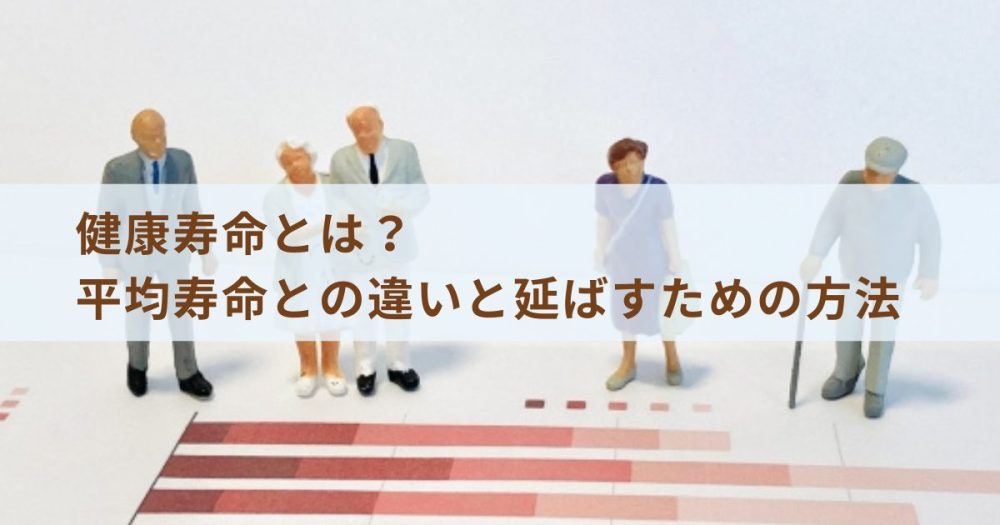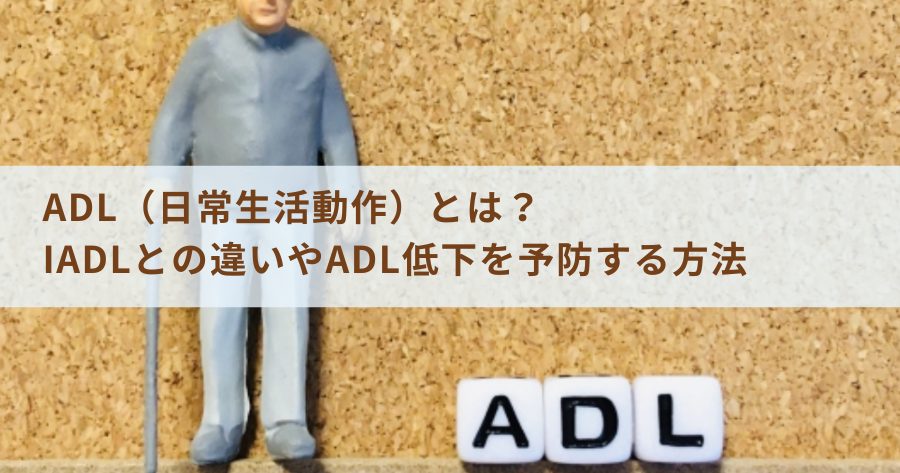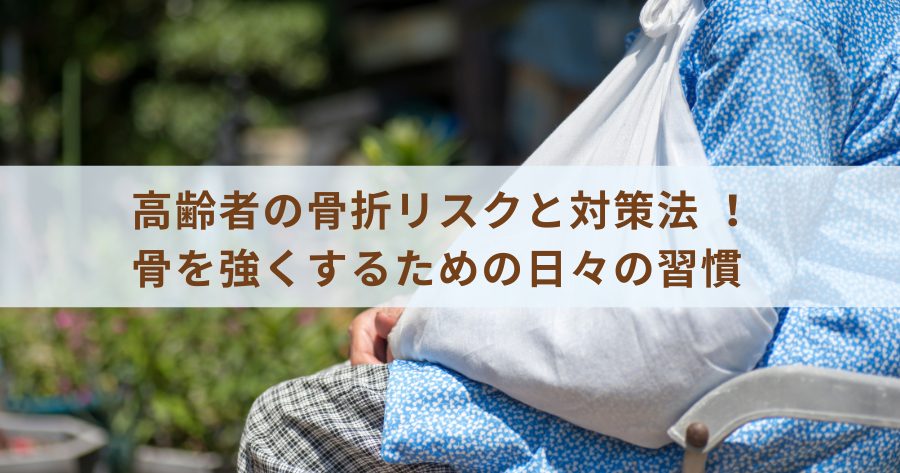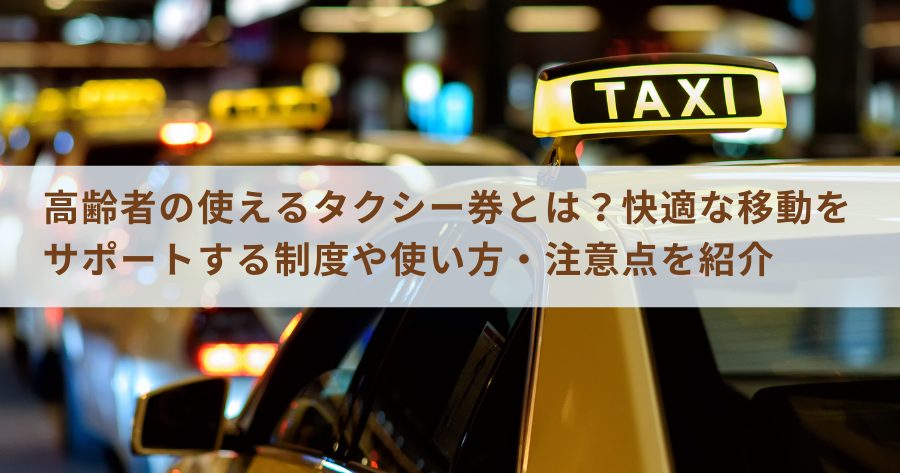介護予防とは?健康な老後を送るためにも重要な予防対策とサービスや制度
- 2024.05.16
最終更新日 2024.5.16.
【シニアカーのエキスパート!シンエンス監修】介護予防をすることは、現代の高齢化社会において健康な老後を実現するための重要な役割をになっています。
健康なうちに取り組むことで高い効果が発揮されるため、思い立ったらすぐに行動できるといいでしょう。
この記事では、介護予防について詳しく解説するとともに介護予防サービスや支援制度、個人で取り組める予防方法などについて紹介していきます。
いつまでも健康に家族と過ごすためにも、介護予防について考えてみましょう。

電動車いす、電動カートのレンタル・販売を行う専門会社。高い技術力と豊富な実績で運転指導からメンテナンスまでトータル的にサービスを提供。そのほか歩行器のメーカーとしても、超コンパクトサイズから大型モデルまでラインナップ豊富に展開。
▷コーポレートサイトはこちら
目次
介護に具体的な予防策はあるの?

介護予防とは、要介護状態の発生をできる限り防ぐ、もしくはできる限り遅らせる取り組みや活動のことをことをいいます。
身体機能の低下や認知症の進行を遅らせることや、すでに要介護状態にある人はその悪化をできる限り防ぐこと、さらには軽減を目指す取り組みのことも介護予防といえますね。
とはいえ、介護に具体的な予防策があるのかどうか、疑問に持たれている人も多いのではないでしょうか。
介護の予防策は、具体的には以下の項目があげられます。
・身体活動の促進
・社会参加の促進
・認知機能の維持
・栄養バランスの改善
・定期的な健康チェック
・健康な生活習慣の維持
質の良い睡眠、バランスの取れた食事、規則正しい排便という健康的な生活習慣を送ることに意識を向け、歩いたり軽い筋トレなどの簡単にできる運動も意志的に取り組むことが重要です。
またサークルやボランティアなどの社会参加をすることで人とのかかわりを深めることが、介護の予防には重要とされています。
介護予防をする主な目的
日本は高齢社会の真っ只中ですが、今後もこの高齢化は上昇を続けていき、世界のどこの国もこれまで経験したことのない超高齢化社会が待っているといわれています。
人生100年時代、健康で長生きするためにも若い時期から健康づくりに取り組み、高齢者になった時に介護が必要な状態にならないように取り組むことが大切です。
しかし単に高齢者の運動機能や栄養状態を改善することだけが目的ではありません。
介護予防の目的は、高齢者が長く自立した生活を維持し、生活の質を向上させることです。
これにより、認知症や身体障害の発症を遅らせ、社会的孤立を防ぎ、医療・介護費用を削減します。
健康に生活ができる状態を通じて、高齢者が積極的に社会に参加し役割分担を持つことで生きがいを感じ、社会全体の負担軽減と生活の質(QOL)を向上させることが重要です。
介護予防とセットで考えられる「フレイル予防」
介護予防と並行して重要なのが「フレイル予防」です。
フレイルは、加齢による身体的、精神的、社会的な脆弱性の増加を指し、未病の状態ともいえます。
人は年を取るとだんだん体力が弱ってきます。
疲れが出やすくなったり、少しの運動で息切れしたり……そうなると外出することが億劫になり家にこもりがちになってしまうこともあるでしょう。
フレイルの状態は、適切な介入により改善や予防が可能です。
介護予防とフレイル予防をセットで考えることで、高齢者が自立した生活をより長く維持し、生活の質の向上を図ることができます。
具体的な予防策には、栄養バランスの取れた食事、定期的な運動、社会参加の促進などがあり、要介護の前段階にあたるこのフレイルを予防することで、未来の介護予防にも繋がることになりますね。
あわせて読みたい記事:「フレイルとは?老後に陥りやすい原因と予防方法などわかりやすく解説」
介護予防には段階がある!ステージごとに説明
高齢者の健康寿命を伸ばすための介護予防には、3段階のステージに分けられています。
それぞれのステージでの予防について詳しく説明します。
一次予防:要介護にならないための予防段階
一次予防の段階では、まだ健康で活動的な状態の高齢者が、要介護状態にならないようにするための取り組みを行います。
具体的には、健康相談やバランスの取れた食事、適度な運動の推進、生活習慣病の予防の予防です。
また健康な高齢者が長く生きがいを持って自立した生活を送ることができるように、社会的交流を促す活動が必要です。例えばボランティアや地域の集いへの参加などにも積極的に参加し、人との交流を持つことも、精神的な充実には大切だと考えられています。
二次予防:フレイル状態などに陥っていないか確認・対処の段階
二次予防の段階では、要支援や要介護状態に陥る可能性が高い、「フレイル状態」の高齢者を早期発見し、対応することで状態を改善するための取り組みを行います。
具体的には、フレイルの早期発見には、定期的な健康チェックや機能評価が重要です。
地域包括支援センターや医療機関と連携し、フレイル状態の高齢者には特化した介護予防プログラムを提供します。これにより、進行を遅らせるか、改善を図ることができます。
三次予防:要介護状態を悪化させないため・改善の段階
三次予防の段階では、すでに要支援や要介護状態にある高齢者が対象になります。
要介護状態の悪化を防ぎ、できる限りの改善や、重症化を予防する取り組みを行います。
具体的には。リハビリテーションや適切な医療・介護サービスの提供を通じて、高齢者が持つ機能の回復や維持を目指します。
すでに発病している病気による合併症の予防と再発防止にも注力し、高齢者が可能な限り自立した生活や社会復帰できる機能を回復・維持することを目的としています。
介護予防が必要?基本チェックリストを使えば自分でも判断できる!
厚生労働省では、介護予防の基本チェックリストを公表しています。
介護予防は介護状態にならないようにするためのもので、健康な状態からはじめなければなりません。とはいえ、自分はまだまだ介護予防なんて必要ないと感じている人も多いのではないでしょうか。
一度自分で基本チェックリストを確認し、介護予防が必要かどうか判断してみましょう。
【介護予防】チェックリスト
「はい」、「いいえ」の頭についている数字を0点または1点としてカウントしてください。
| No. | 質問項目 | 回答 |
|---|---|---|
| 1 | バスや電車で1人で外出していますか | 0.はい/1.いいえ |
| 2 | 日用品の買物をしていますか | 0.はい/1.いいえ |
| 3 | 預貯金の出し入れをしていますか | 0.はい/1.いいえ |
| 4 | 友人の家を訪ねていますか | 0.はい/1.いいえ |
| 5 | 家族や友人の相談にのっていますか | 0.はい/1.いいえ |
| 6 | 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか | 0.はい/1.いいえ |
| 7 | 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか | 0.はい/1.いいえ |
| 8 | 15分位続けて歩いていますか | 0.はい/1.いいえ |
| 9 | この1年間に転んだことがありますか | 1.はい/0.いいえ |
| 10 | 転倒に対する不安は大きいですか | 1.はい/0.いいえ |
| 11 | 6ヵ月間で2~3kg以上の体重減少がありましたか | 1.はい/0.いいえ |
| 12 | 身長 cm 体重 kg (BMI= )(※) | 18.5未満で1点 |
| 13 | 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか | 1.はい/0.いいえ |
| 14 | お茶や汁物等でむせることがありますか | 1.はい/0.いいえ |
| 15 | 口の渇きが気になりますか | 1.はい/0.いいえ |
| 16 | 週に1回以上は外出していますか | 0.はい/1.いいえ |
| 17 | 昨年と比べて外出の回数が減っていますか | 1.はい/0.いいえ |
| 18 | 周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われますか | 1.はい/0.いいえ |
| 19 | 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか | 0.はい/1.いいえ |
| 20 | 今日が何月何日かわからない時がありますか | 1.はい/0.いいえ |
| 21 | (ここ2週間)毎日の生活に充実感がない | 1.はい/0.いいえ |
| 22 | (ここ2週間)これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった | 1.はい/0.いいえ |
| 23 | (ここ2週間)以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる | 1.はい/0.いいえ |
| 24 | (ここ2週間)自分が役に立つ人間だと思えない | 1.はい/0.いいえ |
| 25 | (ここ2週間)わけもなく疲れたような感じがする | 1.はい/0.いいえ |
引用: 基本チェックリスト |厚生労働省
■1から20までの項目が10点以上の場合
これは、日常生活の様々な面で支援が必要かもしれないことを示しています。
特に、基本的な日常生活活動(ADLs)に関連する項目で「いいえ」と回答が多い場合は、要介護や要支援のリスクが高いことを意味しています。
■特に6から10までの項目(運動機能に関連する項目)で3点以上の場合
転倒リスクや運動機能の低下が示されている可能性があり、運動器の機能向上を図る介入が必要かもしれません。
■11及び12の項目(栄養状態に関連する項目)の両方に「いいえ」と回答した場合
栄養不良のリスクが高いことを意味しており、栄養改善のためのサポートが必要です。
■13から15までの項目(口腔機能に関連する項目)で2点以上の場合
口腔機能の問題が示唆されており、口腔ケアの改善が必要です。
これらの基準に当てはまる場合は、さらなる評価や介護予防プログラムへの参加が推奨されます。ただし、これらの数値はガイドラインに過ぎず、個々の状況やニーズに応じて異なる場合があります。
チェックリストの結果に不安を感じた場合は、医療専門家や地域包括支援センターに相談することが重要です。
介護予防で使える予防サービスをうまく利用しよう

介護が必要な状態になった時には、「介護予防サービス」を利用しましょう。
介護予防サービスとは、高齢者ができるだけ長く自宅や地域で自立した生活を送れるよう、早期に予防対策を施すための支援サービスです。要介護状態になることを防ぎ、すでに一定の支援が必要な方の状態悪化を抑えることを目的としています。
介護サービスと介護予防サービスの違いは、「介護サービス」は要介護1〜5の認定の人が利用でき、「介護予防サービス」は要支援1・2の人が利用できるという点です。
さらに介護予防サービスは、①予防給付と②総合事業の大きく2つに分けられます。
介護予防には、食生活の見直し、運動能力の維持、口腔機能の改善などが含まれます。これらは、自宅での自立した生活を長く維持するために重要な要素です。
①予防給付とは
予防給付とは、要支援1や2の認定を受けた高齢者が対象の介護予防サービスの一種です。このサービスは現金支給ではなく、実際の支援としてのサービス(現物給付)で提供されます。
自宅で受けられるサービス(訪問型)や施設に訪問して受けられるサービス(通所型)、地域支援型や地域密着型などがあります。
要支援や要介護状態になる可能性の高い高齢者が受ける訪問型や通所型のサービスもあり、介護予防のための情報提供やボランティア活動などが行われています。
■訪問型
訪問型は、入浴介助サービスや保健師や看護師などが訪問して体調チェックやリハビリを行うサービス、介護福祉士や訪問介護員が訪問して身体介助や家事の手伝いを行うサービスです。また通院が難しい人には、自宅に医師や歯科医師などが訪問し、でいる限り在宅での療養上の管理や指導をしてくれるサービスもあります。
■通所型
通所型は、介護予防を目的としているデイサービスや通所リハビリテーションの施設に通うサービスです。
施設によっては短期宿泊や、長期入所に対応しているところもあります。
■地域密着型
地域密着型の介護予防サービスは、原則その地域に住む住民だけが利用できるということが特徴です。
内容は通所型や訪問型とほぼ同じですが、サービスによっては要支援1の人は受けられないものもあります。
地域支援型のサービスは各市町村が実施しているサービスで、要支援・要介護認定で非該当となった人も利用できることが特徴です。
②総合事業とは
総合事業は、より広い範囲の高齢者を対象とした介護予防のサービスで、地域全体で高齢者の生活機能の維持・向上や生きがいづくりをサポートします。
総合事業は「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」の2つに分かれています。
■介護予防・生活支援サービス事業
介護予防・生活支援サービス事業は、主に要支援の可能性がある65歳以上の高齢者を対象にしており、多様な生活支援ニーズに応えるために設計されています。この事業には、訪問型サービス、通所型サービス、およびその他の生活支援サービスが含まれています。
サービスの提供は、個々の高齢者が持つニーズに基づいて行われ、要支援者が日常生活をより良く、自立して送れるよう支援します。
具体的には、家事支援や機能訓練、栄養改善、見守りサービスなどが提供されます。目的は、要支援状態の悪化を防ぎ、自立した生活を維持することにあります 。
■一般介護予防事業
一般介護予防事業は、すべての高齢者を対象とし、介護予防普及啓発事業、地域介護予防活動支援事業、地域リハビリテーション活動支援事業などから構成されます。
この事業の主な目的は、地域全体で高齢者の自立支援と社会参加を促進し、介護が必要な状態になることを予防することにあります。
活動内容には、住民主体の運動やレクリエーション活動、通いの場の提供、リハビリテーション専門職の活動支援などが含まれます。
これにより、高齢者が地域社会で活動的かつ健康な生活を送ることが促されます 。
介護予防サービスを利用したい場合
サービスを受けるまでの流れは以下の通りです。
①要介護認定の申請
②訪問調査と主治医の意見書
③要介護度の判定
④認定
⑤介護(介護予防)サービス計画書の作成
⑥サービスの利用開始
参考:サービス利用までの流れ|厚生労働省
流れを詳しく説明していきます。
①要介護認定の申請
介護サービスを利用するためには、まず介護保険被保険者証を持って、お住まいの市区町村で要介護認定の申請を行います。40〜64歳の第二号被保険者の場合、医療保険証が必要です。
②訪問調査と主治医の意見書
申請後、市区町村の職員が訪問して認定調査(聞き取り調査)を実施します。また、かかりつけ医による心身の状態を記載した主治医意見書が必要になります。主治医がいない場合は市区町村指定の医師が診察します。
③要介護度の判定
調査結果と主治医意見書を基に、コンピュータによる一次判定と介護認定審査会による二次判定が行われ、最終的に要介護度が決定されます。
④認定
市区町村は審査結果に基づき要介護認定を行い、結果を申請者に通知します。認定は要支援1・2から要介護1〜5までの7段階および非該当(※)に分かれています。
⑤介護(介護予防)サービス計画書の作成
認定結果に基づき、ケアプラン(介護サービス計画書)を作成します。要支援の場合は「地域包括支援センター」、要介護の場合は「ケアマネジャー」に相談します。ケアプランは、利用者のニーズに合わせて、どのようなサービスが必要かを定めるものです。
⑥サービスの利用開始
ケアプランに基づき、介護サービスの利用が始まります。これには、訪問介護、デイサービス、ショートステイなどがあります。
※「非該当」と判定された方でも、市区町村が提供する地域支援事業を利用できる場合があります。
サービスを受けるにあたっては、まず市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談し、適切な手続きを行うことが重要です。
自分でできる介護予防方法

介護予防は、必ずしもサービスを受けないとできないわけではありません。
自分で少し行動習慣を見直すだけで十分に介護予防は可能です。
ここから、自分でできる介護予防の方法をお伝えします。
栄養バランスのいい食事を心がける
介護予防として栄養バランスの取れた食生活を送ることは、生活習慣病の予防にもとても重要です。
また加齢により筋力の低下や衰えから、転倒・骨折のリスクも増えてきます。
日頃からバランスの取れた食事をとることで、生活習慣病や骨粗しょう症にならないように努めましょう。
意外と大切!口腔ケアも忘れずに
忘れられがちですが、口腔ケアを心がけることも重要な介護予防のひとつです。
歯医者に定期的に受診し、毎食後の歯磨きとうがいで口の中を清潔に保ちましょう。
口腔内を清潔に保つことは、歯周病予防につながるほか、心血管疾患や糖尿病、呼吸器疾患など全身のリスクとも関連しているといわれています。
また口腔ケアをすることで、話す・食べるなどの口の働きや舌の機能を維持向上させること
ができます。
食事の楽しみや、人との会話の楽しみが続けられることで、高齢者のQOL向上にも繋がるでしょう。
散歩など継続的な運動をする
介護予防には、普段から適度な運動を継続することはとても重要です。
強度な運動は避け、散歩やストレッチ、軽い筋力トレーニングなどがおすすめ。
適度な運動を心掛けることで、足腰が強くなり転倒や骨折のリスクも少なくなります。
また、生活習慣病の予防にも適度な運動は欠かせませんね。
あわせて読みたい記事:「効果的な散歩の秘訣!効果や注意点を知ってより健康的な生活へ」
人と会話したり交流をもつ場を設ける
人と会話をして、社会と交流を持つことは、介護予防としてとても大切なことです。
高齢者にとって、交流は認知症のリスクを低減し、ストレスも軽減してくれます。
趣味のクラブやサークル、地域の集まりや高齢者向けの施設など、参加しやすい交流の場を見つけておきましょう。
シニアカーは介護予防に役立つ

シニアカーの使用は、介護予防に役立つ可能性があります。
シニアカーは、自力での移動が難しくなった高齢者にとって外出の機会を増やし、活動的な生活を促進する重要なツールです。
普段の買い物や、社交活動への参加が容易になり、これが高齢者の心身の健康維持に寄与するでしょう。そのため、介護が必要になるリスクを低減する効果が期待できます。
車の運転をしなくなったり、長距離を歩いて出かけることに不安を感じてきて外出が億劫になってきたら、シニアカーも検討してみてください。
シニアカーにはGPSの見守りサービスを

とはいえ、高齢者が慣れないシニアカーに乗って1人で外出するとなると、本人はもとより、家族の心配も尽きないでしょう。
そんな時は、シンエンスの電動車いす用モニタリングサービス「モニスタ」がおすすめです。モニスタは、車両に搭載されたGPSデバイスが走行中の電動車いすを常時モニタリングし、日々の使用状況や現在地・消耗品の交換時期などをリアルタイムでお知らせしてくれるサービスです。
ぜひこの機会にモニスタを導入し、利用者もご家族も安心してシニアカーを利用してみませんか?
まとめ:いつまでも健康に過ごすには早くから介護予防を心がけることが重要

「いつまでも元気にいきいきと自分らしく毎日を過ごしたい」ということは誰もが望むことではないでしょうか。
そのためには、早くから介護予防を心がけることが重要です。
適度な運動、バランスの良い食事、人との交流など、今からできることを始めておきましょう。
社会との交流を持ち、自分の役割を見つけることで充実した老後の生活を送れることでしょう。