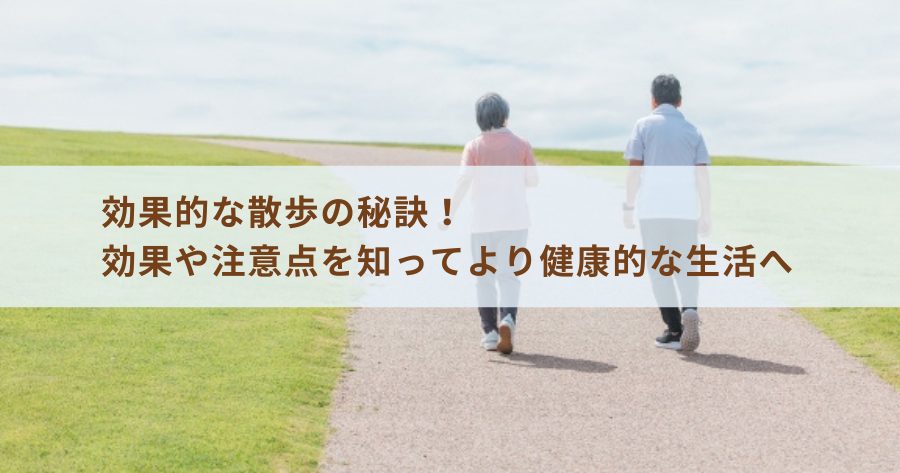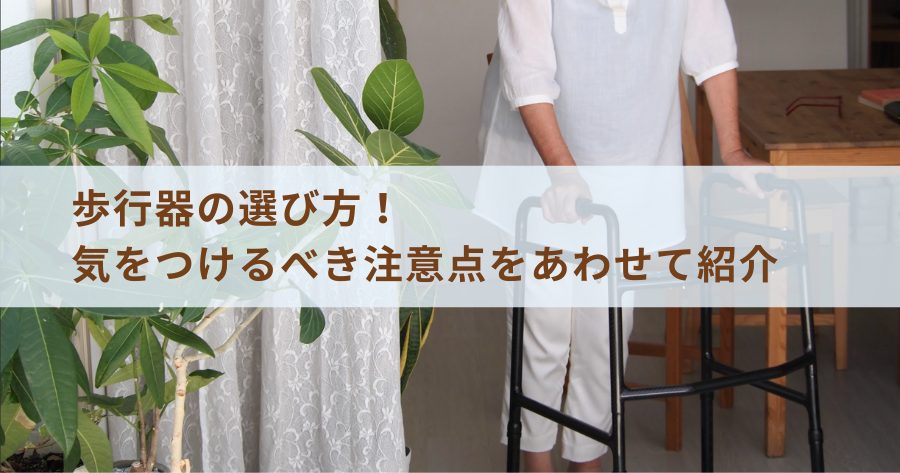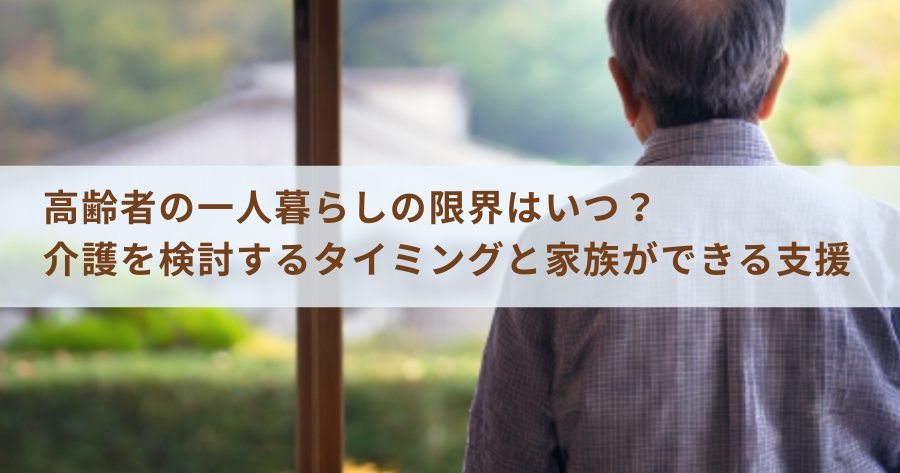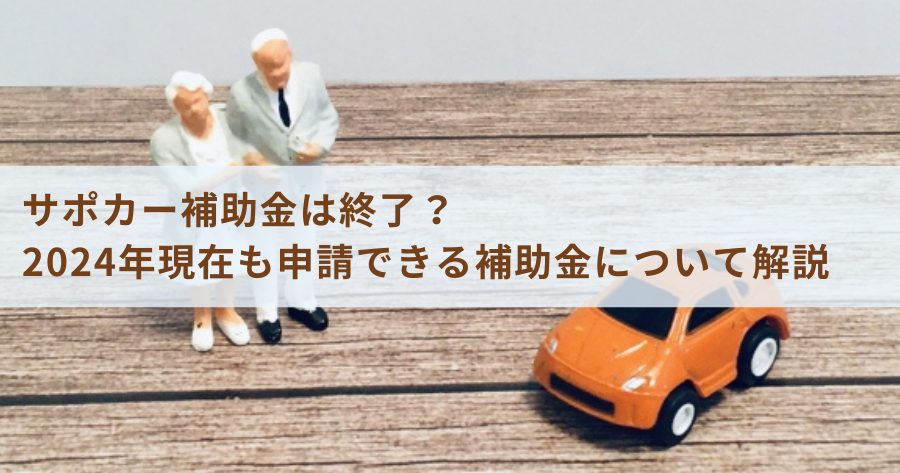高齢者は何歳から?法律での定義や高齢化社会に向けて考えたいこと
- 2024.03.15
最終更新日 2024.4.26.
【シニアカーのエキスパート!シンエンス監修】高齢者は何歳からを指すのか、実はその明確な定義はありません。
日本では一般的に65歳以上を高齢者とすることが多いですが、法律によって高齢者を指す年齢や定義は変わります。
今後、健康寿命が伸びて長寿化が進むと、高齢者を指す年齢や定義が変わる可能性もあるといえるでしょう。

電動車いす、電動カートのレンタル・販売を行う専門会社。高い技術力と豊富な実績で運転指導からメンテナンスまでトータル的にサービスを提供。そのほか歩行器のメーカーとしても、超コンパクトサイズから大型モデルまでラインナップ豊富に展開。
▷コーポレートサイトはこちら
目次
「高齢者」は何歳から?明確な定義はある?

みなさんは何歳からが高齢者だと思いますか?
実は高齢者の年齢に明確な定義はありませんが、日本では一般的には65歳以上とされています。
世界保健機関(WHO)では、65歳以上を高齢者としているため世界的にも65歳以上を高齢者としている国が多くあります。
内閣府が行った年齢・加齢に対する考え方に関する意識調査では70歳以上を高齢者だと答えた人が全体の7割ほどでした。また、年齢で一律にとらえるべきでないとの答えた人も全体の3割以上います。
日本では高齢化がすすみ、2022年10月の時点で65歳以上の人口が29%となりました。平均寿命は伸びつづけ、2021年に男性が81.47歳、女性が87.57歳と長寿です。
一般的に高齢者と言われている60代の人たちは、健康的な人が多く現役で仕事をしている人もたくさんいます。
時代とともに、高齢者に対する感じかたも変化していくでしょう。
高齢者を指す年齢は法律によっても変わってくる
高齢者を指す年齢は、法律によっても変わります。
例えば、以下のような法律があります。
「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、55歳以上を高齢者と定義
「高齢者の住居の安定確保に関する法律」では、60歳以上を高齢者と定義
「道路交通法」では、70歳以上を高齢者と定義
「高齢者の医療の確保に関する法律」では、65歳以上74歳以下を前期高齢者、75歳以上を後期高齢者と定義
また、年齢だけでなく身体の状態で高齢者を定義する法律もあります。
「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」では、心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人と定義しています。
このように年齢によって一概に高齢者を定義できません。
参考:e-Gov法令検索
前期高齢者と後期高齢者の違いは?
前期高齢者と後期高齢者の違いは年齢に基づいています。
高齢者の医療の確保に関する法律では、65歳以上74歳以下を『前期高齢者』、75歳以上を『後期高齢者』と年齢によって定義しています。
公的年金は現在65歳から受給できます。また希望によっては繰上げ(60歳から)受給や繰下げ(66歳以降から)受給することも可能です。
75歳の誕生日を迎えた人(後期高齢者)は後期高齢者医療制度への加入が義務付けられています。今まで加入していた医療保険からの切り替えです。
後期高齢者医療制度は、医療費は原則1割負担となります(高所得者は3割負担)。そのため、75歳以上になると多くの人が医療費の負担が減ります。
高齢者マーク(高齢運転者標識)は70歳から
高齢者マーク(高齢運転者標識)は70歳から義務付けられています。
旧型のもみじマーク、新型の四つ葉マークの2種類あり両方とも使用可能です。
年齢とともに身体能力は低下して、今まで安全運転していた人も運転技術の衰えや判断力の低下が現れます。高齢者マークを使用しないことで現在は罰則はありませんが、使用して周りの車に配慮してもらいましょう。
また、自分でも使用することで運転に注意する意識づけにもなりますね。
あわせて読みたい記事:「高齢者マークとは?何歳から使用すべきかメリットなどあわせて紹介」
今後、高齢者の年齢は75歳以上になる?
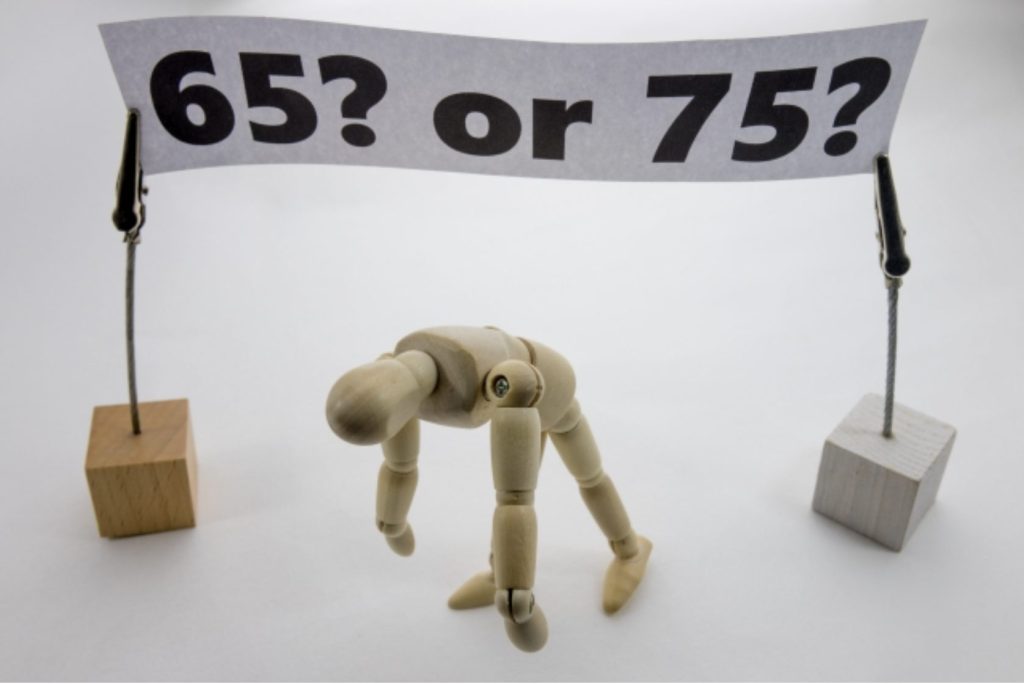
2017年、日本老人学会と日本老人医学会が高齢者の定義についてのワーキンググループを立ち上げました。(※)
議論する中で、「若返り現象」という特に65〜74歳の前期高齢者について、心身や社会活動が可能な人が多いことを訴えています。また以前話した内閣府の意識調査の結果では、60代で高齢だと感じる人は少なくなっています。
これらの結論から、65〜74歳を準高齢者、75歳〜89歳を高齢者、90歳〜を超高齢者と提言し、高齢者を65歳から75歳に見直すべきだと発表しています。
高齢者が75歳に変更になり、定年退職の年齢が高まれば従来よりも働ける期間は長くなります。65歳を過ぎても健康で働きたい人にとってはメリットです。
しかし、デメリットとして公的年金の受給開始時期が遅れる可能性があります。その場合、受給までの生活費は仕事で収入を得る、もしくは今までの貯金や家族が負担することになります。
また、後期医療保険制度の引き上げがあれば医療費の自己負担が増える可能性もありえます。
(※参考:高齢者の定義と区分に関する、日本老年学会・日本老年医学会 高齢者に関す る定義検討ワーキンググループからの提言)
今後、高齢化していく社会で考えたいこと
日本は少子高齢化が進んでいます。
今後もこの社会で生きていくためには、できるだけ健康に生きていくこと、必要な人に必要な援助を行うことが大切です。
そして、今まで高齢といわれてきた65歳以上の人の社会への参加など、社会に貢献できる環境作りが必要になります。
健康寿命を延ばし、高齢者が健康に生きられる社会づくり
健康寿命とは、健康上の問題で日常生活に制限のない期間の平均のことをいいます。平均寿命と健康寿命が近いほど、元気に生活できる期間が長いということです。
日本の健康寿命は、平均寿命の延びを上回っています。若い時から健康に心がけていると高齢になってからも健康状態がよい人が多くみられます。
また、若い世代に比べ、高齢になるほど運動習慣があるとの調査結果があります。
健康を維持するために、若い時から散歩やスポーツなど運動習慣をつけるのはおすすめです。喫煙や過度な飲酒も避けた方が良いでしょう。
そのほかにも、趣味を持つ、地域活動へ参加するなど社会関係をもつことで、新しい出会いや日々の生活にメリハリがつき満足感や充実感が生まれます。健康でいることで生きがいを感じることができます。
運動習慣や社会活動など生活の中に取り入れて健康寿命を伸ばしましょう。
あわせて読みたい記事:「健康寿命とは?平均寿命との違いは?健康に長生きするために日常生活でできること」
介護や支援が必要なお年寄りの生活をサポートする方法
高齢化に伴い、要介護者は増加しています。高齢者の介護をするのが高齢者という老老介護も珍しくありません。
生活をサポートする方法として、介護保険制度を使ったサービスの利用や福祉用具貸与などがあります。
また、今までのような移動が困難になっている人のために、シニアカー(電動カート)や電動車いすが普及してきました。これらのパーソナルモビリティを導入することで自分で移動でき、生活の幅が広がります。
結果、要介護者のQOLの向上につながります。また高齢化社会において介護する側の負担を軽減する目的でもおすすめです。

シニアカー(電動カート)や電動車いすの利用をより快適にしてくれるのが「モニスタ」のGPS見守りサービスです。
「モニスタ」があれば、外出の状況や安全運転ができているかなど確認できるため安心です。
シニアカーのタイヤやバッテリーなどの消耗部品の交換の目安も教えてくれるので、突然の故障なども防げます。
シニアカーを使用するときには、ぜひあわせてモニスタを利用してみてください。
高齢になっても働き続けられるようなキャリアプラン
心身が健康で働く意欲がある高齢者は多くいます。
理由は、収入のためや仕事にやりがいを感じているなど人それぞれです。高齢化によって継続雇用や定年の引き上げなど法律が改定されています。
いつまで自分は働き続けていくのか、どのようなキャリアを築いていくのか考えてみてください。今までの経験を生かして社会に貢献したり、得意なことで新たな仕事がみつかるかもしれません。
早くから老後の生活を考えておくことで準備ができ、気持ちの面でも焦りません。
まとめ:高齢化社会により、高齢者の定義は今後変わっていく可能性も

高齢化社会により、今後高齢者の定義は変わっていくかもしれません。
定義が変わると仕事や金銭面に影響がでる可能性もあります。
長寿の国、日本で今できることは日々の生活の中で健康に気をつけ、健康寿命を伸ばすことを意識してみてください。また自分のキャリアを見直し、人生100年時代にそなえていくことも大切です。
高齢者のQOLの向上のためにも、生活の幅が広がるシニアカーや電動車いすの選択をおすすめします。自身で行動できることは、結果、健康寿命を延ばすことにつながるでしょう。
シニアカーを使う場合は、あわせてモニスタの見守りサービスがあれば安心安全な移動ができます。
自分にあったサービスを利用して、充実した老後を迎えましょう。